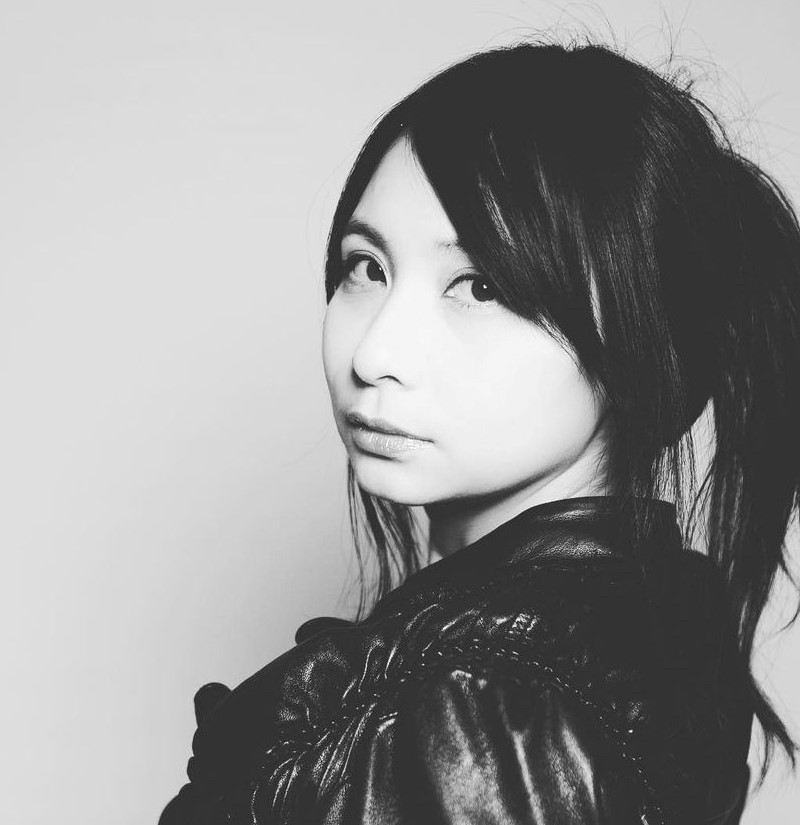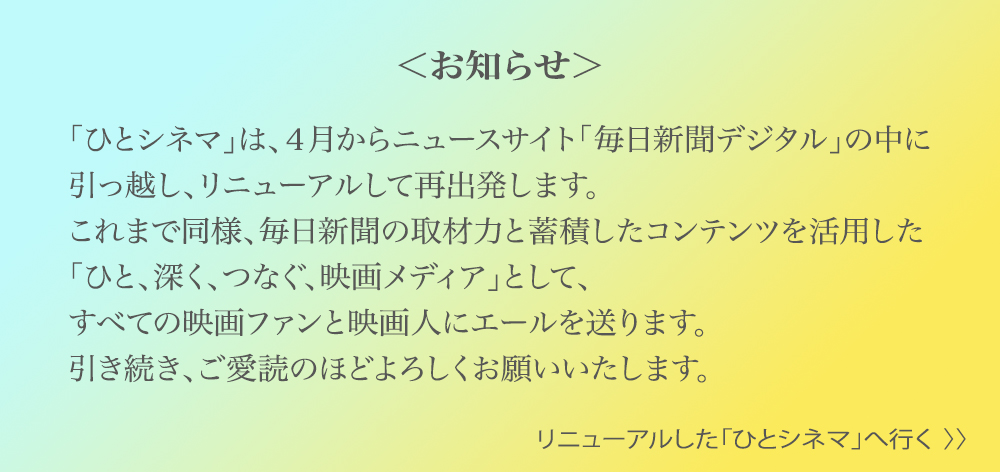公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「アトムの心臓『ディア・ファミリー』23年間の記録」を語る清武英利 撮影:下元優子
2024.6.10
一つの新聞記事をきっかけに「ディア・ファミリー」原作「アトムの心臓」23年間の記録: 原作者・清武英利インタビュー
無謀な挑戦を「どうしても書き残しておきたかった」
映画「ディア・ファミリー」(毎日新聞社など製作委員会)は心臓に難病を抱え余命10年と宣告された娘と決してあきらめなかった一家の実話である。家族らと親交を重ね、この物語を「アトムの心臓『ディア・ファミリー』23年間の記録」として刊行したのはノンフィクション作家の清武英利。一つの新聞記事をきっかけに長年にわたって丹念に取材を重ねてきた。「運命にあらがう人間を書くことができた。そして、映画は人の持つ無限の可能性を正面から描いています」と語る。
筒井(映画では坪井)宣政(のぶまさ)さんは、愛知県春日井市でホースなどビニール樹脂加工の小さな町工場を経営していた。次女佳美(よしみ)さんは「三尖弁(さんせんべん)閉鎖症」という先天的な病気を抱え、幼い頃に医師から「手術はできない。温存すれば10年は生きられる」と言われる。全国の病院を回ったが診断は同じ。宣政さんは「俺が作る」と人工心臓の開発に立ち上がり、妻陽子さんと勉強に励み、資金と時間をかけるものの次々と問題が立ちはだかり、研究は行き詰まる。その努力はやがて日本初の医療機器「IABPバルーンカテーテル」の製作につながる。次女の命の灯と引き換えに、約17万人の命が救われたのである。
23年前の一つの記事がきっかけだった
2001年、清武は読売新聞中部本社社会部長に着任すると、朝刊の第3社会面に丸々1ページの「幸せの新聞」を始めた。当時は倒産が急増し、暗く苦しい話が紙面を覆っていた。清武は「苦しみをできるだけ前向きに捉えよう。挫折しても立ち上がる人の話、その瞬間を伝えたい」と編集長としてすべての原稿に目を通した。創刊から3カ月、山下昌一という若い記者が宣政さんと佳美さんの話を書いてきた。
「最後の夜、佳美の大好きなクリスマスの賛美歌を歌いながら、心電図の波が消えるまで見送った。……あの子は自分が助からなくても、救われる人がたくさんいることを喜んでいるだろう。……」。400字詰め原稿用紙3枚に満たない記事だった。自然に涙が浮かんだ。「泣かせようという原稿ではない。こんな話が世の中にあるんだと思い、心から感動した」。紙面に写る宣政さんはがっちりした体格のしぶとそうなおじさんだった。どんな人生を歩んだのか、いつかは本に残したいと考えたが、当時は多忙を極め、同時に「開発物語だけではないはずだ」という気持ちもあった。「この家族との縁の糸はつないでいこう」。それが後年役に立った。
佳美さんの青春、人間像が足りない
11年11月、読売新聞グループと決別した時、自分の手の中に残っていたのは書くことだけだった。「批判することよりも、批判される側や対象になって書く方が好きだ。晴れ晴れと生きる人の姿を書こうと思った」。長年の取材の中で、いつかは書き残したいと思っていた人々を実名のノンフィクションで書き始めた。
それが「しんがり 山一證券最後の12人」(講談社ノンフィクション賞)、「石つぶて 警視庁 二課刑事の残したもの」(大宅壮一ノンフィクション賞読者賞)などに結び付いたが、書いても書いてもなお書き足らない。無名の偉人が声もなく埋もれているのに、書く人がいない。それを文芸春秋の編集者に話すと連載が決まった。タイトルは「後列のひと」(後に「後列のひと 無名人の戦後史」として出版)だった。
後ろの列の目立たぬところで人や組織を支えてきた人たちの物語である。不器用でも真っすぐに生きてきた人に光を当てた。「後列のひと」を書こうと思った時、「筒井さんの事がすぐに頭に浮かんだ」。それまでも、はがきのやり取りをしたりして親交を温めていた。
ただ、バルーンカテーテルにつながる開発物語だけでは足りないことは分かっていた。開発の話は宣政さんや陽子さんから何度も聞いている。足りないと思ったのは「23歳で亡くなった佳美さんの青春だ。佳美さんの人間像が分からない。彼女の青春が全く分かっていない」。はっきりとした強い口調で語った。「筒井夫妻にいろいろ聞いたがどうしてもわからない。夫妻や姉妹、親しい友人たちの心の底には、あのころの喪失感を二度と味わいたくない気持ちがあったようだ。だから口が重く触れたくない感じだった」
新聞記者は人の一番過敏なところにも土足で入っていく。しかも、清武は実名主義を貫いてきた。「実名は自分や事実に正直であることの担保でもある。ところが、実名主義は時間がかかる。信用してもらうにはどうしても時間が必要だった」

信用を得る時間が必要だった
宣政さんが佳美さんの結婚をめぐる話を突然漏らしたのは21年。人工心臓の開発に苦闘した痕跡を求めて、東京大学や東京女子医大付属病院を一緒に回っている時だった。「立ち寄ったそば屋で、彼は思い出をかみしめるように話し始めた」
「宣政さんは、佳美さんは結婚したら死ぬ、命を縮めることになると思っていた。思い出したくない話だったのかもしれない。最後にはやっと生きているような状態だったから。それは支えてきた人の正直な思いだった。その時から、これが彼女の青春だと思って神経を集中して話を聞き始めた」。筒井さんに加えて、姉妹や友人、いろいろな人に一から聞いて歩いた。そのまま書くにはいかないことも含め、佳美さんの青春が徐々に見えてきた。
本格的に再取材をしてから6年。「今振り返ると、取材の中で唯一の壁のようなものだったのは佳美さんの青春、人間像であり、それを越えられるかであった。どうしても、その壁を乗り越えないでくれと言われたら、開発物語により特化した、詳細なものになったかもしれない。でもやはり、足りないピースは拾い集めなければならない、というのが正直な気持ちだった」
長い間、宣政さんだけでなく、家族や周囲の人たちと接点を持っていたからこそ、なんとか応じてくれた。「1、2年では無理だった。時間をかけることは大切だ。僕はほかの取材でも、1年間ぐらいは信用してもらう準備期間だと思っている。その準備期間を終えた次の物語も僕の中にはたくさんあって、その取材をこつこつと同時に進めている」
泣ける喜び、ほれぼれする人
「あの子は自分が助からなくても、救われる人がたくさんいることを喜んでいるだろう」。それが宣政さんの原動力になった。高名な研究者が「無知で鈍感であるがゆえにまっすぐ」と宣政さんを言い当てた。「鈍感な開発力の持ち主が、人間の可能性に限界がないことを実証した。信念を持ってやってきたことを知ってもらいたい、という気持ちも彼にはあったでしょう」
清武は多くの時間を筒井家と共にした。「宣政さんは、娘の死が自分たちにもたらしたもの、なんとかできる命は救いたいという思いでやってきた。他の記者が来ても取材に協力したと思う。私は最後の執筆のバトンを受け継いだ記者に過ぎない」と謙遜するが、信頼の上に築かれた関係であったことは疑う余地はない。
「宣政さんは、ずんずんと前に進んでいく。ワンマンで、おやじらしい人というべきか」。取材にはいつまでも付き合ってくれた。インタビューは電話も含め20回近く、1回短くて2時間、長いと8時間にもなる。エネルギーの塊のような人」。奈美さん、寿美さんの姉妹らの証言も含めてすべてテープ起こしをした。相当の分量だが、長い取材ではそれが有効だったという。「筒井さんは、全部理解してもらいたいという気持ちが強くあった」。「後列のひと」の連載では、宣政さんと陽子さんに限って、夫婦で上下編にし、1回に原稿用紙20~30枚になった。
「宣政さんは強引で欠点もあり、自分でも『私は善人だとは思っていませんよ』という。そうでなければ不可能をひっくり返す開発や会社経営はできない。そういうむき出しの一貫したところにひかれたんですよ」と表情をやわらげる。「彼や家族のけなげさは、実は誰の心のなかにもある。ただ、貫くことは難しい。だから表に現れるとき、心が晴れて、ほれぼれするような気持ちになる。そういった家族や人々を書くのがノンフィクションの幸せです」。社会や企業の最前列にいても、つまらない人は書かないし、やめてしまうのだ。
「掘ってみて、青春が分かった。つるはしを振るって金脈にあたった。書いていて時々、泣けちゃうなって思うのも喜びでした」。自らを鉱夫作家と例えた。鉱夫記者、鉱夫ライターでもある。「毎回感じるのですが」と前置きして、こうつないだ。「これだけ時間がかかったのは、事実が待っていてくれたからです。事実は頑固なもので、鉱夫や耕夫が掘り当ててくれるのをじっと待っていると思うのです」
清武は構成やコンテを何度も書き直す。時には短冊にエピソードを書いて入れ替え、何度も構成を練る。「僕が手をかけられるのは構成だけです。破綻したらまた作り直した。原稿は何とかなっても、構成がうまくいかないと続かない」。ノンフィクションでも読むときのゴツゴツ感をなくして読みやすくすることに苦心した。引っかからないように読めるよう心がけた。

©2024「ディア・ファミリー」製作委員会
取材メモから脚本づくりへ
ここからは映画化の話だ。「話をいただいたのはコロナ前で、メモや資料の集積の段階。映画は水もの、本当にできるのか当てにならない時期でもあったが、ぼんやりとした希望みたいなものだと思っていた」。WOWOWではこれまでの作品を3本ドラマ化していたので信頼があった。「映画人は粘り強い」とも感じた。東宝も同時期に筒井さんを紹介した番組を見て動いていた。映画はお金もかかるし、時間もかかる。「何か足りない、とずっと考えていた時だったが、ここまでに書いてくださいというメドにもなった」
この作品は清武の連載記事や取材メモをベースに、林民夫が脚本(最終的に21稿)を書き、本格的にスタートした。「一部にせよ、詳細なメモを見せることはめったにあることではなかった」。メモは取材の大事なところだけ残して要約していた。「取材とメモはどんどん進み、それも共有したが、私が筒井家の鈍感開発力や家族愛に加え、佳美さんの生への希求と青春を書いたのに対し、映画は困難な開発と家族愛を正面から描いた。そこが本と映画が少し異なるところだが、私は悲しみよりも希望を押し出そうという映画人の信念を感じた」
それが映画制作者と筒井さんを仲介することにもつながった。映画は佳美さんが亡くなって、そのあとの希望と17万人の命を救い、今も救い続けていることを主軸に置いている。連載と取材メモから作り始めたが、「僕から注文は一切していない。別の才能だから。志が同じであれば、映画と本は違っていいと思っている」と歯切れがいい。