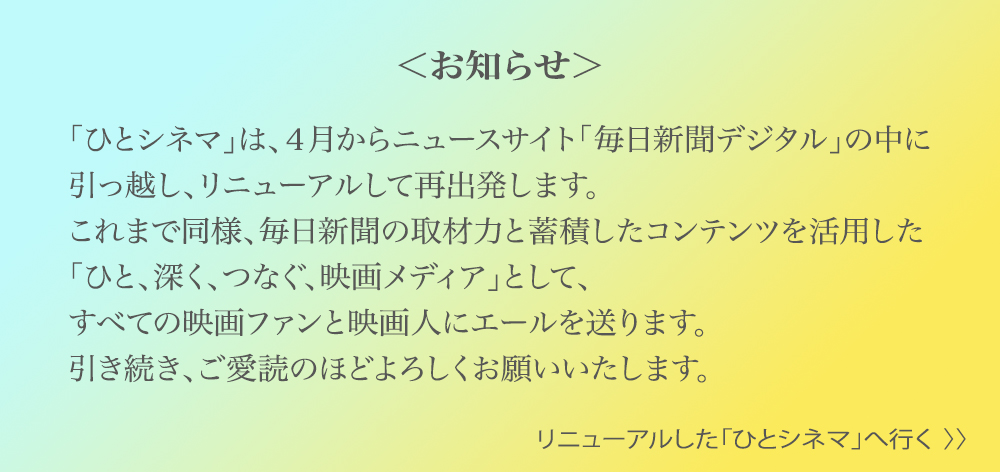2021年に生誕90周年を迎えた高倉健は、昭和・平成にわたり205本の映画に出演しました。毎日新聞社は、3回忌の2016年から約2年全国10か所で追悼特別展「高倉健」を開催しました。その縁からひとシネマでは高倉健を次世代に語り継ぐ企画を随時掲載します。
Ken Takakura for the future generations.
神格化された高倉健より、健さんと慕われたあの姿を次世代に伝えられればと思っています。
インタビューに答える降旗康男監督=東京都千代田区で2017年3月22日、中村藍撮影
2022.4.15
映画と歩んで:監督・降旗康男/上 財務状況聞き東映入社
高倉健の作品の多くをともにした映画監督・降旗康男。
惜しまれながら2019年5月20日に逝去されました。
彼の遺作「追憶」の公開前に思いを語った「映画と歩んで:監督・降旗康男」その上・中を再掲載します。
17年3月28日掲載。
*()の年齢は掲載当時のもの
「駅 STATION」「夜叉(やしゃ)」「鉄道員(ぽっぽや)」――。2014年に死去した高倉健を主演に、数々の名作を世に送り出してきた降旗康男監督(82)。それらの作品を撮影したカメラマンの木村大作(77)と9年ぶりにタッグを組んだ新作「追憶」(毎日新聞社など製作委員会)が5月6日から全国公開されるのを前に、これまでの映画人生を語ってもらった。
東映のほうが財務状況がいい
1934年、長野県松本市で、祖父も父も国会議員という名家に生まれた降旗。終戦直後の多感な高校時代に、映画との関わりが生まれた。「当時、松本には映画館が七つあった。遠方から汽車で通学する同級生は朝が早いので午前中は部室で寝ている。私が代わりに授業で代返し、午後は彼らに代返してもらって、私は映画館に繰り出していた」と振り返る。
戦前のフランス映画、アメリカの西部劇、戦争を生き延びた日本の映画人がつくる映画を順番に鑑賞した。中でもフランス映画に影響を受けたという。「ハッピーエンドでも、ヒーローものでもない、ちょっとペシミスティックなフランス映画に引かれていった」
フランス映画を見るうち、日本語の字幕がでたらめなことに気付き、同級生とフランス語の勉強会を開いた。「フランス語の文法を習得し、おかげで東大にも合格した」と笑う。
東大仏文学科に進み、57年東映に入社。さぞかし、映画への情熱に燃えていたのかと思いきや、そうではなかったという。「当時、文系の大学生の就職先で給料が高い順で、東映と東宝が3、4番目だった。銀行員だった叔父から『東映のほうが財務状況がいい』と言われて」と意外な動機を明かす。
映画づくりの原点
東映に入り、早速、助監督として現場に出たが、予算の配分を巡って反目があり、撮影が始まるとスタッフたちがどこかに行ってしまう。「家城巳代治(いえきみよじ)監督とカメラマンの宮島義勇(よしお)さんの現場で、残ったのは私ともう1人の新人だけ。2人でエキストラを動かしたり、撮影現場を整えたり。それが実地訓練になった」と振り返る。
ある日、忙しい宮島カメラマンに「代わりにカメラをのぞいておきなさい」と命じられた。初めて見るカメラの黒いフレームの中で、俳優たちが躍動していた。「ああ、映画というのはカメラのフレームの中で生み出されるのだ、と強烈に感じた」と語る。それは降旗にとって映画づくりの原点となった。宮島からは映画製作のイロハを教えられたという。「宮島さん、木村大作さんと、私は本当にいいカメラマンに恵まれた」と感謝を口にする。
「降旗―高倉」コンビの映画で描かれた世界の原形
66年、緑魔子が主演の「非行少女ヨーコ」で監督デビュー。そして、2作目の「地獄の掟に明日はない」で、後に長い付き合いとなる高倉健を主演に据える。スターシステムを取る東映の中でも、高倉は当時、一押しのスターだった。
長崎を舞台にした同作で、高倉は被爆した若いやくざを演じる。原爆症と闘いながら、任俠(にんきょう)道の筋を通そうとする男。過去を背負いながら真っすぐ生きる主人公の姿は、後の「降旗―高倉」コンビの映画で描かれた世界の原形だ。
「本当はもっと原爆症を中心テーマに据えた物語を考えていたが、直前で別の若手が監督することになり、脚本も東映のやくざ映画ふうに書きかえられた」と明かす。ところが、撮影期間が実質20日しかなく、その若手には無理となって、降旗にメガホンが戻ってきた。「原爆症の要素を入れて脚本を書き直しながら撮影を続けたが、一度、できた脚本を直すことは至難の業。脚本の持つ力を思い知らされた」と振り返る。
ただ、同作を見ると、当時の日本人にとって被爆が身近な問題であったことが伝わる。その頃、高倉は富司純子の父、俊藤浩滋プロデューサーが手掛ける「日本俠客伝」や「昭和残俠伝」シリーズなどの任俠映画に出演していた。その中で、同じやくざを演じていても、人間の内面を照らした「地獄の掟……」は毛色が違う。「健さんが、当時の奥さんの江利チエミさんから『もっとこういう映画に出ればいいのに』と言われたとうれしそうに語っていた」。興味深いエピソードである。
時代の流れに合わせ、降旗もまた任俠映画を撮るようになった。「『地獄の掟……』を撮ったことで、『あいつは短い期間でもそれなりの映画をつくる』というありがたくない定評を得た」と苦笑いする。それでも、「俊藤さんは映画づくりや興行に細心の感性を持っていた。数年間は一心同体で映画をつくった。悔いはない」と監督としての初期の時代を振り返る。
だが、隆盛を極めた東映任俠路線も70年代に入ると、菅原文太らが活躍する実録路線に取って代わられる。そして、降旗にとっても大きな転機が到来するのだった。