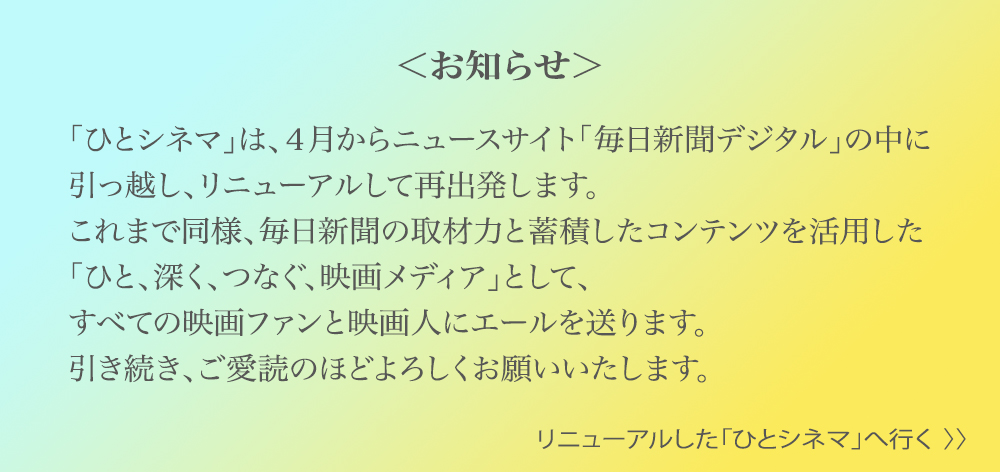公開映画情報を中心に、映画評、トピックスやキャンペーン、試写会情報などを紹介します。
「零落」を監督した竹中直人=三浦研吾撮影
2023.4.04
斎藤工に自分で出演交渉 竹中直人「『零落』は絶対撮りたかった」
映画を撮るのが楽しくてしょうがない。公開中の新作「零落」は「原作を本屋で読んで絶対映画にしようと思った」とほれ込んで、自ら原作者の浅野いにおに映画化を打診し、主演の斎藤工とも直接出演交渉。撮影現場も無駄なく楽しくと、スタッフの負担軽減を図る優良監督だ。
「東京・赤坂のTBSの前にあった書店に並んでいて、『零落』というタイトルと帯に描かれた目にくぎ付けになった」。原作漫画の帯には登場人物の1人、〝猫の目〟をした女性、ちふゆの目元が描かれている。「絶対映画にしようって」
「作るのに必死だった」
しかし、まとまりかかった出資話が白紙に戻るなど、道は平坦(へいたん)ではなかった。前作「ゾッキ」(2021年)では「1人じゃ無理」と、人気俳優の斎藤工と山田孝之に声をかけ、共同監督という形で実現。「零落」も「『ゾッキ』の宣伝期間中、工とご飯食べてる時に『零落』って知ってる?って聞いたら、読んでます、大好きですって」。じゃやろうよ、やらせてくださいと話が進んだ。
「原作を読んですぐ、自分のラジオ番組にいにおさんをゲストに呼んで、映画化したいとお願いしました。脚本が完成する前に撮影稿を自分で書いて、都内をロケハン。いにおさんには撮影稿やロケハンの写真も直接送ったんですけど、後から普通は出版社通しますって言われちゃって」。とにかく「作るのに必死だった」というのである。

「零落」©2023浅野いにお・⼩学館/「零落」製作委員会
「夜の歩道橋に縦書きのタイトル」画が先に浮かんだ
映画化は「この原作を画(え)にしたい」と思うところから始まるという。「『零落』は夜の歩道橋に、縦書きのタイトルが出るイメージ」。監督デビュー作の「無能の人」(1991年)では、「石を売っている主人公の横にタイトルが現れる画があった」。
しかし原作に忠実にというわけではない。「漫画なら、原作の構図に引っ張られない。突き放してとらわれない。『零落』は原作にあったか分からないけど、海を出したい、橋を出したいと決めてました」。斎藤は原作の漫画家、深澤とかけ離れているが「独特の深澤を作ってくれました」。一方原作のちふゆを演じた趣里は生き写し。「キャスティングが決まれば、役作りしなくていい」という演出だから、今回は「完璧」と満足げだ。

「メッセージを込めるタイプではないかな」
「無能の人」もつげ義春の漫画が原作だったし、どちらも主人公が描けない漫画家なので、「売れる」漫画を描くことへの反発と、「売れたい」という思いにもんもんとする。ただとぼけたユーモアが漂った「無能の人」と比べると、「零落」の主人公の葛藤はより複雑で悲観的。30年間の、表現者・竹中直人の変化を映しているのかと思いきや。
「成長してないです。メッセージを込めるとか時代に向けて作るというタイプではないんでしょうね。内容は原作でできあがってるから、画と音楽が浮かびます。『無能の人』はつげさんが気に入ってくれたらうれしかったし、『零落』もいにおさん1人に向けて、セッションするつもりで撮りました」
「無能の人」のラストシーンは、主人公の漫画家が妻と子と手をつなぎ、夕景を3人で歩く後ろ姿だった。「ほのぼのしていると言われたけど、実は主人公はどこでも飛んでいけるはずなのに、家族にがんじがらめになってるっていうつもりだった。3人だけの孤独のイメージ」。と聞けば「零落」の深澤も孤独にさまよい、売るための漫画を描くことになって、自由は手にできない。「昔から変わっていないんじゃないですか。毎回ゼロに戻って、新鮮な気持ちで取り組みます」

今回の発見は、画像の縦横比が1:2.35と横長のシネマスコープの画作りだった。10年来の付き合いという撮影の柳田裕男から「シネスコでしませんか」と提案された。「作りづらいと思っていたんですけど、顔の上下が切れてる構図で芝居が撮れるというのが大発見でした。『零落』はこの画、と思えたんです」
撮影は定時終了「スタッフの負担軽減したい」
竹中組の現場は無駄がない。俳優としてテレビ、映画で無数の現場を踏んできた経験が蓄積されている。「いろんな現場でスタッフの大変さを感じているから、自分の現場は能率的に進めようと思っています。いつまでかかってるんだと思うことがあるし、監督のこだわりとか根性とかは嫌い。休みなく働くような撮影はしたくないし、無理なスケジュールは組まない。定時に安心して帰れるのがいいです」
現場ではモニターを見ず、カメラ横が定位置。リハーサルは繰り返さず、テストしないで本番にいくことも。キャスティングで演出は終わりと、俳優を信頼するのも自身の経験からだ。
「昔の監督はカメラの横にいて芝居を見てくれた。その方が面白いですよ。現場では台本を持ってなかったと思うし、自分も持ちません」。「エキストラも主役」と助監督任せにせず、みずから演出するのも変わらぬ作法だ。

「1億出す」と「無能の人」
高校時代から8ミリカメラを回し、多摩美術大では自主製作に夢中だった。「監督にはなれない」と思って俳優の道に進み、人気者に。出演した「226」(1989年)の撮影中、「映画の話ばっかりしていたら、プロデューサーの奥山和由さんが『そんなに映画好きなら監督すれば。1億円出す』と言ってくれて」。「無能の人」はベネチア国際映画祭で国際批評家連盟賞や毎日映画コンクールの日本映画優秀賞、スポニチグランプリ新人賞などを受賞。以来、30年以上。
企画は常にあるが「自分が面白いと思うものはマニアックで、早々には通らない」とか。それでも「撮りたいという気持ちは、衰えてないと思います」と意欲は満々なのだ。