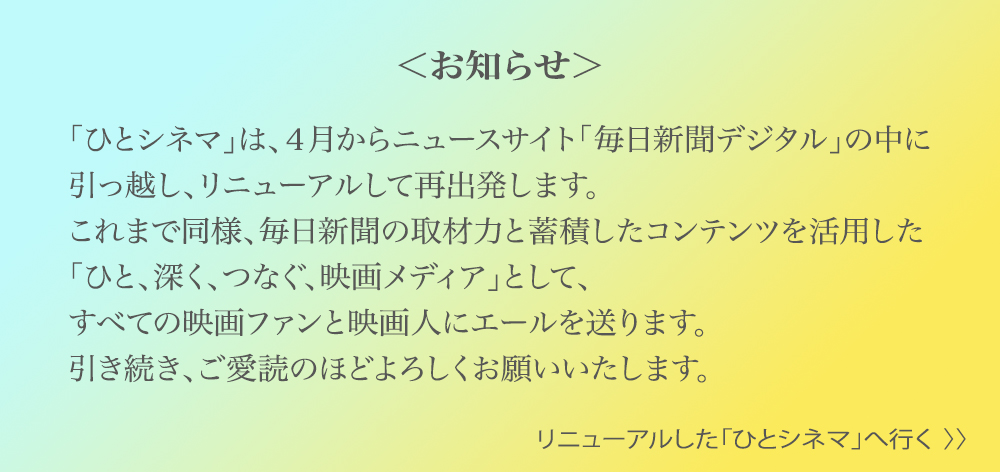誰になんと言われようと、好きなものは好き。作品、俳優、監督、スタッフ……。ファン、オタクを自認する執筆陣が、映画にまつわる「わたしの推し」と「ワタシのこと」を、熱量高くつづります。
©2024「帰ってきた あぶない刑事」製作委員会
2024.6.08
「あぶ刑事」を始めた男のデスクから振り返ってみる「帰ってきた あぶない刑事」80年代完結! だが――今もハマでふたりは疾り続ける
80年代の完結、そして〝あぶ刑事を始めた男〟との出会い
ようやく長い長い、1980年代が終わった。そう思う。テレビ放映から少し後の90年代初頭、東京・麴町のNTVドラマ班で助監督をしていた頃だ。倉田貴也ディレクターの初演出作の割本を本館地下のコピー室で大量に刷り、ホチキス留めをしようと空きデスクを探していた。そこへ大きなショルダーバッグを下げたプロデューサーが「ここ、使って良いよ」と言ってくれた。普段使っていないのか、そのデスクの上は物が少なくて広かった。ドサリとコピーを置いてホチキスを探すが見当たらない。「これ、使いなよ」とそのプロデューサーはどこからかホチキスを出し、針と一緒に渡してくれた。デスクでホチキスを留めていて、ふと目を上げると、目の前には「あぶ刑事」のシナリオが並んでいる。
「!?」、そうそれは〝「あぶ刑事」を始めた男〟初川則夫プロデューサーのデスクだったのだ。もう読みたくて読みたくて仕方がない。ヨダレを垂らしながらホチキス留めをしていると「読みたいなら、読んで良いから」と、そう初川さんは言ってどこかへと去っていった(残念なことにNTVにいた間は、もう二度と初川さんとは会う事は無かった)。よほど物欲しそうな目をしていたからに違いない。空き時間に「もっと あぶ刑事」の最終回「一気」を読ませてもらう。大川俊道脚本だ。キャストスケジュール等、さまざまな制約の中、最終回らしい熱量と気迫で書かれた玉稿だった(最終回前辺りのサブタイトルは舘ひろしさんの都合で、柴田恭兵さんの出番の方が多い展開となっていた)。エアチェックのVHSを擦り切れるほど幾度も観(み)た、忘れられるはずもないシーンが次々と眼裏に浮かぶ。いま考えると過去作品とは言え、関係のない若手スタッフに脚本を読ませてくれるなど、実におおらかな時代だった。そしてそれは、後進を育てたい初川さんの優しさだったのだと思う。
ハマの脈流、黒澤満と伊地智啓
「渡り鳥」シリーズを代表とする日活無国籍映画、その流れを東映に引き込んだ黒澤満のセントラル・アーツ、そしてさらに分岐して角川映画との伝説の連動を生んだ伊地智啓のキティ・フィルムという流れの中で生まれた奇跡が本作だった。こんなフィルム製テレビ映画が1986年には毎週制作されていたという機運、参集したクリエーターたちのならず者のような爆熱と、50年代日活の頃から続くハマのエッジ感――2024年の今になって、ようやくあの80年代の鼓動を、そんなふうに冷静に受け止められるようになった。初川さんの企画を黒澤さんが番組に組み上げたという。セントラル・アーツの制作体制にキティ・フィルムの伊地知さんが合流、ここに邦画の最前線的な布陣が完成した。現場は2社の同根スタッフばかりだ。長谷部安春を筆頭に村川透、手銭弘喜、西村潔、そして後に当作で監督デビューする一倉治雄、成田裕介と、あの時代の日本映像界の背骨とも言うべき面々がメガホンを取り、脚本も伝説的な丸山昇一を皮切りに、柏原寛司、田部俊行等々、その後の映画界を支える巨匠たちの作品が、贅沢(ぜいたく)にもテレビで毎週観られた訳である(助監督には鹿島勤も!)。
憧れの伊地智さんとはついに仕事をする事は適(かな)わなかったが、満さんとは東映ビデオの劇場作品で幾本かご一緒することができた。お会いする前は荒事育ちの活動屋だとばかり思っていたのだが、そんなふうは一切無く、とても物静かな紳士だった。企画の内容を現場担当から聞き、都度、とても的確な指摘を下さる校長先生のような印象の方で、企画の穴をさまざまな角度から塞いで頂いた事を覚えている。
麴町梁山泊
また一方で、その流れを編成の核に据えたNTVという局の鷹揚(おうよう)な構えにも言及するべきだろう。倉本聰、山田太一と組んだ重鎮、石橋冠が率いるNTVドラマ班。「池中玄太80キロ」をはじめとする〝土曜グランド劇場〟の黄金時代は過ぎ去って、視聴率戦争に後塵を拝していたとしても、その制作モラルを揺るぎ無く貫いていた。「前略おふくろ様」の吉野洋、前出の「あぶ刑事」初川則夫、「家なき子」「教師夏休み物語」の井上健、後に同局のエポックとなった「ぼくの魔法使い」や「花田少年史 幽霊と秘密のトンネル」で伝説の水難シーンを撮り上げた水田伸生、「金田一少年の事件簿」「ごくせん」「家政婦のミタ」等ドラマにとどまらず映画「カイジ」でも大活躍した佐藤東弥……ここではとても書ききれないが、麴町がもの凄(すご)いクリエーターたちの梁山泊のようだったことは間違いない。自身は大失敗の連続だったのだが、怒られるよりも可愛がってもらった記憶の方が勝っている。毎日デスクの玲子さんの美しい笑顔に癒やされながら、ユージのように走り回り、トオルのように怒鳴られっぱなしの毎日だった。撮終後に南館の道路向かいにある〝ラ・タベルナ〟で奢(おご)ってもらう、牛肉の薄切りステーキ&バターライスとビールのなんと美味(うま)かったことか!
16ミリテレビ映画からの進化
さて思い出話はここまでにして、作品の内容について書いていきたい。かつてのシリーズといちばん違うのは、今作はデジタル撮影という事だ。当時のテレビ映画は16ミリ撮影で機動力がある一方、恐らくは現場にはビジコン(フィルムキャメラの撮影映像を現場で確認できるビデオシステム)は無かっただろう。現場は撮影部・照明部の熟練の技量に支えられて撮られていたのではないか。今回はHD-camで余すことなく俳優部とハマの風景が追われている。ゆえにさまざまな時間帯の光線に遠慮の無い、豪勢な画作りとなっている。フィルムの場合、ナイトシーンや屋内の撮影では露光と照明にかなりの慎重さが求められ、アクションシーンには焦点等、現像所からラッシュが戻ってこないと確認には不安が残る時代だった。しかし当作ではかつてのニュアンスをしっかりと残しながらCG合成も大胆に取り入れ、アクションやスローモーションでも高精細な解像が銀幕では確認できる。フィルム傷や汚れも懐かしい〝アジ〟ではあるが、デジタルだと俳優部の表情が格段に精緻に記録される。CGはやや甘い気もするが、もともと当劇場版シリーズは破天荒なCG合成も多く、狙いのようなユニークさもあって、むしろ安心する映像となっている。
無論、テレビシリーズを愛してやまないファンたちへのサービスもたっぷりある。原廣利監督は原隆仁監督の子息ということだが、さすが旧作スタッフ2世だと思わされるのが、画角サイズやキャメラポジションが旧作のルールに準じている点だ。おそらく撮影部も若い方々だろうに実によく練られており、監督がしっかりと撮影体制をグリップしている印象だった。音楽の使い方もかつてのファンを裏切らない演出で見事である。
大川俊道・岡芳郎の脚本も絶好調だ。オリジナル・ライター故の筆致が冴(さ)え渡っている。大川俊道担当の1st.テレビシリーズ第36話「疑惑」で描かれた振り子の正義、岡芳郎が担当した同第32話「迷路」の群像等、旧シリーズの名作を彷彿(ほうふつ)とさせる展開となっていた。「あいつがトラブル」でも採られていた、キャラクターから物語を書き起こしていき、整合性を牽引(けんいん)する、その大川手法は健在である。観客が納得せざるを得ない勢いとキャラクター造形が徹底して脈動する。80年代初作という古さは一切感じさせない、冒頭から結末までのピーキーなフルアクセル感は、現代感覚の映画としても過不足は一切無い。
そして俳優部だが――これについてはとても拙稿では語ることはできない。跳ぶ、走る、転がす、撃つ、撃たれる、歌う、叫ぶ――ここまで書けばお分かり頂けるだろう。読者にはぜひ銀幕で確認してもらいたい。そうすれば次回作を期待する気持ちも分かってもらえるはずだ。
完結から始まる、終わらないハマの伝説
そっと横目で見る観客たちの表情や、思わず零(こぼ)れる歓声を聞いていると、映画館が満さんや伊地智さんの時代、テレビも映画も熱かったあの80年代に帰ってきたようで、そして終劇後にはそれがふっと消え去ってしまったようで、冒頭の〝80年代完結〟という気分になった訳だ。
しかし――それはやっぱり、イヤだ。まだまだ80年代には暴れてもらおう。
さあ、次作は「帰ってきた もっと あぶない刑事」だ。