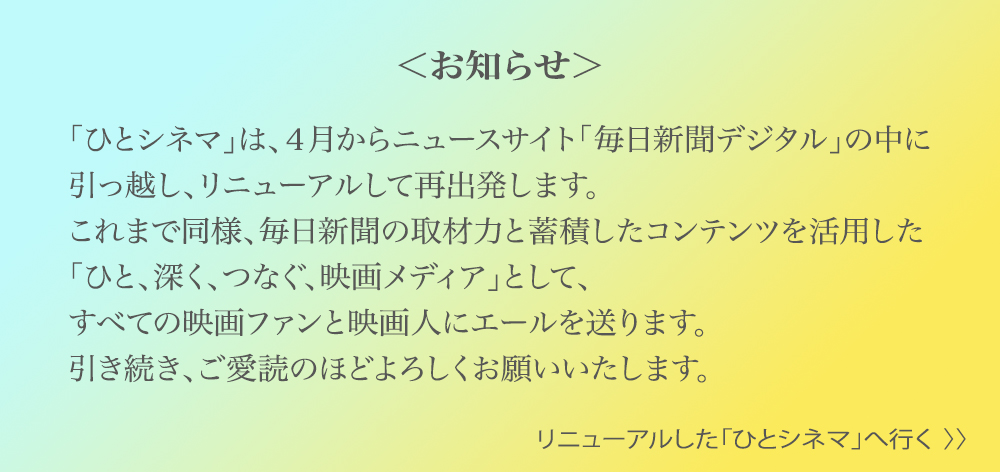シンガーソングライター波多野奈央さんが書いた映画コラムを読んで、元キネマ旬報編集長・関口裕子さんがこうアドバイスをしました(コラムはアドバイスの後にあります)
自分が心引かれる方向を見つけるのは、途方もない一生の旅
映画同様、記事の冒頭も、KTタンストールの「Suddenly I See」から入っていく。彼女が2004年にリリースしたアルバム「Eye to the Telescope」に収められた曲で、パティ・スミスの音楽に出合ったときの衝撃を歌にしている。
「それはなぜ私にとって大きな意味を持つのか」と、何を目指すべきか悟らせてくれた人との出会いを歌うこの曲。映画にぴったりだが、物語が始まる前に流れるため聴き飛ばしてしまいがちだ。にもかかわらず、エッセーの書き出しとしたのは、シンガー・ソングライターの波多野菜央さんの強みだろう。
そんな波多野さんのエッセーで読みごたえがあるのは、やはり〝 アンディと私 〟の見出しがつけられたパラグラフ。シンガー・ソングライターとしての自分と、ジャーナリストへの取っ掛かりとしてファッション誌の編集者見習いとなったアンディを並べて語り、その心情を浮かび上がらせる。
〝 プラダを着た悪魔〟のような上司、ミランダの叱咤(しった)を成長のためのエネルギーに変え、きれいになっていくアンディにワクワクしながら、語るのは一つのジャンルを極めることの難しさ。「エンターテインメントの世界は自由度が高い分、生き方もさまざまだ。その中で自分が心引かれる方向を見つけるのは、途方もない一生の旅ともいえよう」とは、クリエーティブな仕事に携わるすべての人に共通する悩みだといえよう。
そんな波多野さんにはぜひ、商業的題材の極みともいえる「バービー」を、強い作家性で描き切ったグレタ・ガーウィグ監督について書かれることをおすすめしたい。きっと面白い切り口を見つけ出してくれると期待がやまない。
バランスよく、さまざまな要素をちりばめ、飽きずに読ませる手腕にも優れているが、もっと詳細に、音楽、または波多野さんの思考の世界に踏み込む部分があってもいいのかもしれない。
波多野さんのエッセイ
ずるい。ずるすぎる。何がって、冒頭間髪入れずに流れるイントロ。
KT Tunstall の「Suddenly I See」。名作に負けないどころか、これから始まるストーリーにえたいの知れない胸騒ぎを感じさせる、彼女の少し乾いたクールな声とメロディー。これ以上にマッチする楽曲は他にないだろう。驚くのは、この映画のために書き下ろされた曲ではないということ。ニューヨークの街並みに乗せて流れる最高の音楽。初っぱなから感服だ。何度聞いても、こんな曲が書きたいと憧れてしまう。
That’s all 以上よ
ジャーナリストを目指しニューヨークへやってきた、アン・ハサウェイ演じる主人公のアンディ。ひょんなことから、ファッション業界最大の影響力を持つ「ランウェイ」の編集長のアシスタントとして働くことになる。そして、ここのボス、ミランダこそがタイトルの「プラダを着た悪魔」。絶対的存在であるミランダ。悪魔であり、女王蜂である彼女の要望は、仕事にとどまらず双子の娘の宿題まで。NO なんて選択肢はない。質問もしてはいけない。アンディはろくに名前も呼んでもらえない。ボスの口癖は、早口で指示をした後、あきれた時、ピシャリと放たれる〝That’s all〟(以上よ)。
元々ジャーナリスト希望で、ファッションにも興味がなかったアンディは、度が過ぎる要望と雑用に疲弊していく。ミランダは私を嫌っている。どんな頑張りも彼女は認めようとしない。上司のナイジェルに愚痴をこぼすが「君は努力していない、甘ったれるな」と一蹴されてしまう。ここでスイッチが切り替わったアンディは、彼の協力によって「ランウェイ」のオフィスにふさわしいファッションに身を包むようになる。私がこの映画で最も好きなシーンだ。上等な服に身を包んだアンディの自信は画面越しにも伝わるほど、その場の空気を変えた。ゾワッと鳥肌が立つほどに(もちろん世界的スターのアン・ハサウェイなのだから、美しいに決まっているが)。
ここから私たちは〝へこたれない女、アンディ〟の怒涛(どとう)の巻き返しを楽しむことができる。

頭が良くひたむきなアンディは、ミランダの右腕としてキャリアを積み、終盤ではパリのコレクションへ同行する重要な人材となる。ボスの口癖’〝That’s all〟も、アンディの仕事ぶりに声色が変わっていく。さあ、最終的に主人公はどんな道を歩むのか? ニューヨークの街、ファッション業界。華やかな世界が舞台に見えて、仕事、生活、恋愛に友情、共感できるポイントがたくさんある。絶妙なバランス感がこの作品のうまいところだ。
ミランダは本当に悪魔?
幸か不幸か、私はミランダほど突き抜けた上司に出会ったことはない。彼女のように、いかなる相手にも手を緩めない姿勢は、ひそかに憧れる人間像でもある。さすがにやりすぎだと思う部分も多いが、彼女にはその冷徹さを裏付ける経験と知識と自信がある。キャリアウーマンとして多くの犠牲を払い築き上げた彼女のポジション。だからこそ効くパリでのワンシーン。アンディを信頼し、ついに心を開いたノーメークにガウン姿のミランダの素顔は、ひとりの女性で、ひとりの母親だった。彼女は涙と孤独をさらけ出しつつ、それでもやっぱり強かった。

アンディと私
アンディは不本意ながらファッション業界に入ったが、私の場合、シンガー・ソングライター、アーティストとして、強い憧れを持って今この業界にいる。アートの世界、エンターテインメントの世界は自由度が高い分、生き方もさまざまだ。その中で自分が心引かれる方向を見つけるのは、途方もない一生の旅ともいえよう。いかにオリジナリティーを見いだすか、その中にどう大衆性を結び付けるか。歌を届けるためには? 聞いてもらうためには? その時、一番大事な〝思い〟を置いてきていないか?
活動において、正面から斬ってくれる存在はとても貴重だ。それが憧れの方なら尚更に。私自身、最近そんなありがたい機会があった。正直少し寝込むほど厳しい言葉もいただいた。ただ、打ちのめされてからが重要だ。その感覚をどう自分の地図に書き起こしていくか? ここで必要なのが「プライドと信念」だと思う。痛いところと、強い思いをうまく照らし合わせて道を見つけるのだ。
強く、美しくあるために
登場人物全員、プライドが高い。この表現は日本ではあまり良い印象ではないが、ここではとても良い意味だ。泥臭くて、すがすがしくて、きらめいている。ミランダもアンディも違うベクトルの確固たる信念を持ち、我が道を行く。めげそうになった時、一番強い味方は自分だ。私は本気でそう思っている。大丈夫、そう心で唱えるためには、自分の言葉や活動に誇りを持っていなければならない。そのために曲を書き、言葉を探している。
ゾクゾクする化学反応を起こしながら、映画は終わっていく。ラストシーンの 2人の表情は素晴らしかった。思い返せば、冒頭の KT Tunstall の声からも彼女の内なる思いが感じ取れる。ファッションがストーリーの大きな軸にある「プラダを着た悪魔」。身につける美と対比して描かれているのは、それぞれのプライドと信念。誰かに見せつけるものではなく、内からにじみ出る、誰にも奪えないもの。
強く、美しくあるために、私が持つべきものはなにか?それを気づかせてくれた作品だった。
ディズニープラスのスターで配信中
ディでズニープラスで