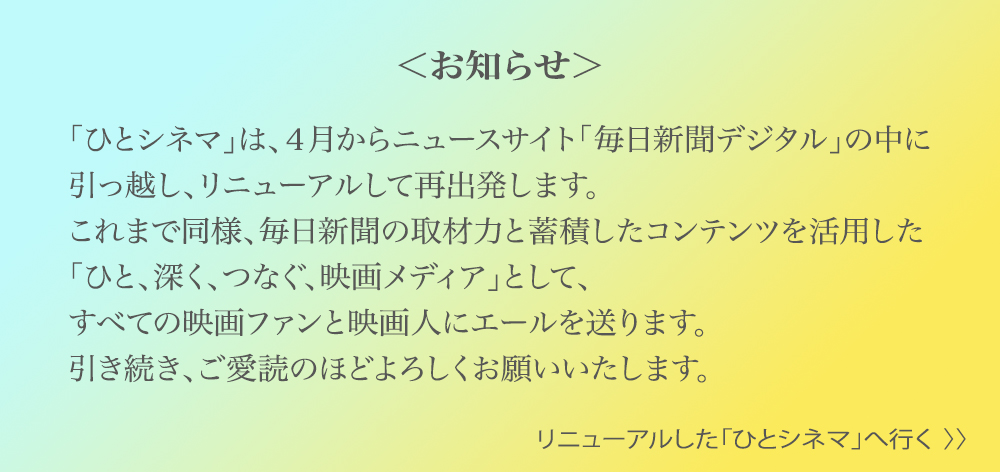誰になんと言われようと、好きなものは好き。作品、俳優、監督、スタッフ……。ファン、オタクを自認する執筆陣が、映画にまつわる「わたしの推し」と「ワタシのこと」を、熱量高くつづります。
「ルックバック」© 藤本タツキ/集英社 © 2024「ルックバック」製作委員会
2024.7.23
<ネタバレあり>まるでコンテンツ従事者の踏み絵のような作品である「ルックバック」 二次制作の功績にも理解と顕彰が必要だ
初期衝動
初期衝動が人生を造形していく素晴らしさと同時に、故に何かを失う酷薄さ、才能の邂逅(かいこう)とは必然であり、幸福でありながら残酷さと表裏であることを描いた作品。「バクマン。」はリアルな設定の上に描かれたファンタジーだったが、当作は人生の射幸と喪失があまりにも現実的で恐ろしい。自身にこんな喪失が訪れたら一体どうなるか――考えただけでそら恐ろしい作品である。
当作は一見、感性の離合を描いているようで、実はまったく逆のものだ。魂が引かれ合った者同士は、必ずもう一度再会をしようと、それぞれの時間を食(は)んでいく。その結末のひとつを描いている。同時にヒトの魂から出力されたものに対する理不尽な抗議は、不意にテロリズムのように襲い掛かることがあると改めて警告してくれている。
物語の素直さ
物語は極めて単純だ。才能の開花は自身によって行われたのではなく、自身を花として見てくれた他者により初期衝動が発動したことによる。才能たちは再会するために散開し、再会は思いがけない暴力によって無惨にも破壊され、永遠の別れが訪れる。終劇時にとどめなく湧き出す感動は、観客に「感動にはストーリー上の変化球やギミックなど一切必要無」ということを自覚させてくれる。とても素直で純粋な物語だった。
青くはやる時代に
中学時代、友人たちと漫画の同人誌を作り続けたことを思い出した。勉強もせず、彼女も作らず、夏休みはクーラーの利く図書館で、冬休みはコタツでひざを突き合わせ、この映画と同じようにわき目も振らずに描き続けた。クリエーターになったのはいちばん絵が下手だった私だけだ。映像監督たちに「編集うまいね」と言われるのは、この時にコマ割りをしまくったお陰だろう。皆何かに取りつかれたように描き続けていた。理由は自分たちでも分からなかった。互いに自作で相手をうならせてやろうと、ひたむきに描き続けた。藤野の背中と同じである。描き続けて数年が経過し、気づくと漫画よりもリアルを撮影できる、映画の世界にたどり着いていた。
やめようと思ったのも同じである。「こんなにうまいやつがいる」と思った瞬間、投げ出した。けれどもかぶとを脱いだ相手からの賀状に「あなたの作品は絶対にまねができない」と書かれていて、藤野のように魂を揺さぶられ、もう一度、作劇の世界に戻ったのだった。こんな経験をしたクリエーターたちは、きっと世界中にいるに違いない。そしてそんな彼らから時代を動かす作家が生まれていることも間違いないのだ。当作の動輪が優れているのはこの点だ。ヒトによってはそれがスポーツであったり、ダンスであったりとさまざまであろうが、居ても立ってもいられない、表現するしかない情動は、恋愛感情や3大欲求をはるかに超える、ヒトの生の証明でもある。ここから物語は走り出す。
キャラクターたちと同年代の声
5年前のあの事件の時。テレビ番組からコメントを求められ、死者が出ていることを理由に断ろうとしたが、「産業にとってどれほどの損失なのかを専門家の口から語ってほしい」と請われ、複雑な心境で話したことを思い出す。実写は機材の進化によって随分と撮影がしやすくなったが、アニメーションはむしろ市場からの要求の難易度が上がり、その期待に応えるための工程はずっと複雑になり、人手も増えることとなった。同時に著作権の保全と侵害の排除もずっとずっと複雑になって、社会からの攻撃も格段にひどくなった。制作者としては現在のアニメーションの制作には手間や傷つくのが怖くて、とても参加できる気がしないというのが本音である。あの事件の犠牲者の数と悲しさは圧倒的であり、絶望しかなかった。クリエーティブを束ねて発力し、発表するにはいろいろな意味であまりにも危険な時代となった。
一方で、私の研究室生たちは当作に強く引かれていた。「背景ごと動く描画、あれはドローン映像をトレースしたのか?」「光線と光量で表現する時間経過、背景画をデジタルで変色させた?」「プロになった藤野が描きながら電話しているシークエンス、あのカットの積み重ねを実写で撮ってみたいが、あの暗さだとうちの機材ではムリか?」――そして、「殺されたけど〝描き続けられる〟って、つまり〝生きている〟ってこと?」「それでも描かないと自分をも裏切ることになる。いや読者を裏切るのでは?」──撮ることの技術的探究と欲求、作品意義へ近づこうとする意志が研究室中に充満する、公開からのこの1週間である。
実写を超える描画表現
作品は心象だけで全編を描いていて、その意味でも画期的な作品だ。CG(コンピューターグラフィックス)や無機的な彩色を避け、肉眼や肉感を大切に表現されている。同時に至極、実写的な映像設計がなされている。近年、「もはや実写で良いのでは?」と思うような精細なアニメーション作品が増えているが、本作に関してはこの感想はまったく間違っていると断言する。驚くことにクライマックスでのサイズ設計は実写と同じでありながら、アニメーションの特質も最大限に引き出す神業的なまでに高度な描画がなされている。むしろ「これは実写では不可能だ」と、そう痛感せざるを得ない、実写がアニメーションに勝てないことがあると思い知らされた瞬間だった。読者にはぜひ銀幕で確認いただきたい。
技術的には学生たちも分析するように、実写的な描画とアニメーションならではのレイアウトのコンバインが見事である。無駄でこれ見よがしなCGなどなく、〝手描きの味〟と〝日本的風合い〟によって季節の移り変わりを丁寧に描いており、ディテールの積み重ねによって説得力のある地方のリアルを生んだ。省略ではない、集約されたアウトラインが驚異的なキャラクターの訴求力をもたらしているのだが、これをわずか2年程度で完成させたこと自体が奇跡である。
河合優実の芝居をしない芝居
メインキャストであるが、俳優を起用することによっていわゆる声優芝居ではない、リアルな声質が獲得されている。「PLAN75」で見せた、河合優実の芝居をしない芝居は本作でも発揮され、それが作劇に大きな効果をもたらした。リアルを積み重ねた俳優部と音響監督には脱帽である。
原作のコマとコマの合間をあぶり出す
脚本的には主人公ふたりの関係が慣熟していくディテールや家族風景を大胆にオミットしながらも、魂が神の領域へと近づいていく様を描く。その道は孤独で冷淡であって同道する者を求める。同時に同道者への依存と煩悶(はんもん)、そして逃れられない初期衝動の感得と恩讐(おんしゅう)、そして喪失と再生がすべて詰め込まれている脚本だ。原作をそのまま映画化したのではなく、原作のコマとコマの合間をあぶり出す文脈が、本作の素晴らしさだと言える。
2次制作の最高峰
原作に近づけることが感動を生むのではない。本作の感動とは2次制作者の原作への精神的傾倒と同化により生まれたものでありつつ、2次制作者の脳髄より出力されたものによって組成されている。原作者もそれを理解し、承認というよりも満足を表明している。近年、かまびすしい原作原理主義だが、「0→1」である原作と同様に、「1→10」の2次制作の功績にも理解と顕彰が必要だと、眼前にたたきつけるような作品だった。
クリエーターはどれほどの悲しさにまみれようが、襲い来る死をのみ下し、表現を刻み続ける覚悟が必要だと本作は告げる。まるでコンテンツ従事者の踏み絵のような作品である。
さてコンテンツ事業の志望者諸君、冥府魔道を行くか戻るか、当作を見てから決めなさい。