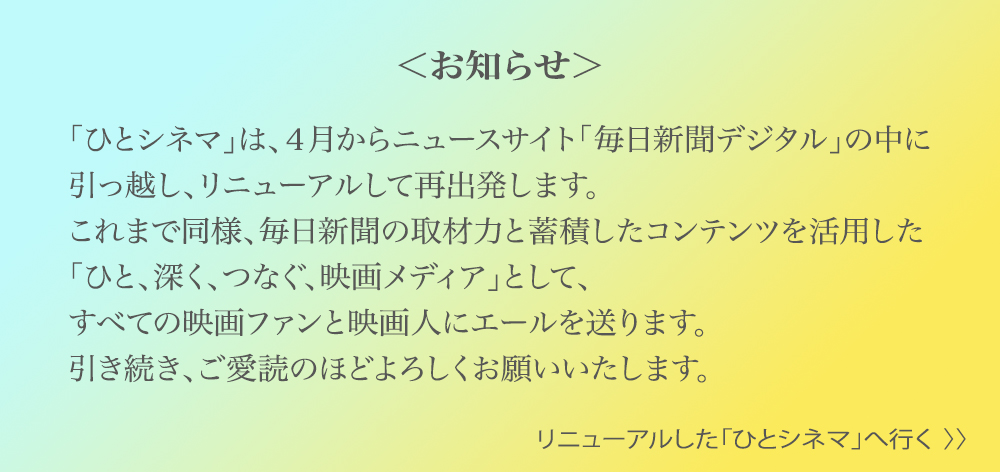毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。
「動物界」©2023 NORD-OUEST FILMS-STUDIOCANAL-FRANCE 2 CINÉMA - ARTÉMIS PRODUCTIONS.
2024.11.08
この1本:「動物界」 〝解放〟のメタファー
往年のオオカミ男ものから「ザ・フライ」「ロブスター」まで、人間が動物に変身する映画は枚挙にいとまがない。当然ながらそれらはホラーやSFジャンルに属するが、フランスのセザール賞で12部門にノミネート(そのうち撮影賞など5部門を受賞)された本作は、比類なき新鮮なインパクトを放つ。一組の父子が織りなすヒューマンドラマであり、現代的な社会批評もはらむ独創性豊かな快作だ。
人間が動物に変異する原因不明の奇病が流行し、フランスでは政府が〝新生物〟と呼ばれる患者の強制隔離を行っていた。料理人フランソワ(ロマン・デュリス)は高校生の息子エミール(ポール・キルシェ)を伴い、新生物と認定された妻の移送先の南仏に移り住む。ところが妻が行方不明になり、エミールの身にも動物化の症状が表れる。
本作の斬新さは、市民が生活を営むごく普通の日常空間に新生物を出現させたことにある。親子が渋滞に巻き込まれている冒頭シーンでは奇怪な鳥人間が大暴れし、スーパーマーケットの鮮魚売り場には腹をすかせたタコ人間が出没。意表を突いた描写の巧みさ、アナログとデジタルを組み合わせた特殊効果のクオリティー、いずれも見事だ。
これが長編2作目のトマ・カイエ監督は、ハリウッド風のモンスター映画とは一線を画す視点を貫いた。半分は人間である新生物を敵視する者と、共存を望む者との対立や分断を描出。さらに新型コロナのパンデミックに似た社会状況を背景にして、奇抜な物語に現実感を吹き込んだ。
そしてカイエ監督は、南仏の森林や湿地帯のロケーションをダイナミックにカメラに収めながら、常に主人公の親子を中心にすえた。動物化の影響で五感が鋭くなっていくエミールの情動を生々しく表現し、不完全な父親であるフランソワの苦悩と人間的な成長も描き出す。どこかギクシャクしていたこの父子が、心を一つにして疾走するクライマックスの高揚感たるや圧巻のひと言。それは、まさしく社会の閉塞(へいそく)感を突き破る〝解放〟のメタファーなのである。2時間8分。東京・新宿ピカデリー、大阪ステーションシティシネマほか。(諭)
ここに注目
この手のSFはえてして人間中心主義的で、人間でなくなることへの恐怖とか、人間でなくなった存在への嫌悪といった感情に訴えるのが常道だ。しかしエミールは、はじめこそ懸命に症状を隠し、否定しようとするものの、森の中で鳥人間と知り合って態度を変えてゆく。自然環境の激変を実感し、人類を脅かす疫病も生々しく体験している現代で、人間優位は空手形。窮屈な規範に縛られ、社会問題に苦しむよりも、いっそ自由に。チラリとエミールをうらやましく思ったのは、こちらも病んでいるからか。(勝)
ここに注目
〝新生物〟とは何か。最初に想起されるのは移民である。受け入れがたいものへの恐怖が先に立ち、それが排除や攻撃に変わる現代社会の一面を映し出す。移民への反発、排斥の動きが強まっているヨーロッパの一部ではなおさらだ。同時に根深いルッキズムがあることも明らかだろう。新生物の描写でも、動物が本来持つ以上の暴力性はないようだ。一方で学生たちの会話などからは、外見の異様さを嫌悪、強調する姿勢が見て取れる。見る者の内面にはびこる偏見や恐れを刺激し、多様な解釈を生み出す作品。(鈴)