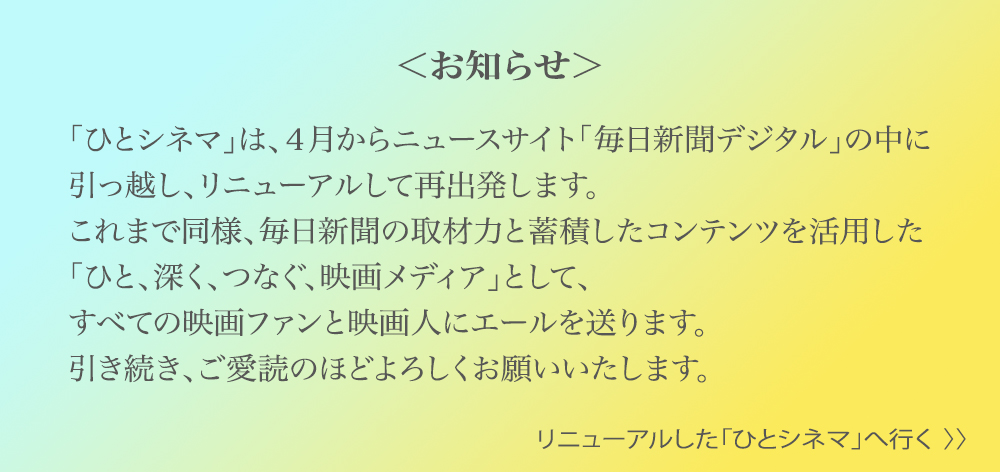毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。
「シビル・ウォー アメリカ最後の日」©2023 Miller Avenue Rights LLC;IPR.VC Fund II KY.All Rights Reserved.
2024.10.04
この1本:「シビル・ウォー アメリカ最後の日」 観客は戦場に没入する
映画の舞台は内戦状態の米国だ。合衆国から離脱した〝西部勢力〟と政府軍が戦い、反乱軍は首都に迫っている。戦場カメラマンのリー(キルステン・ダンスト)と記者のジョエル(ワグネル・モウラ)は、14カ月も取材を受けていない大統領への単独インタビューの特ダネを狙ってワシントンDCへ向かおうとしていた。ベテラン記者、サミー(スティーブン・マッキンリー・ヘンダーソン)とカメラマン志望のジェシー(ケイリー・スピーニー)も同行し、4人は車で首都を目指す。
観客が与えられる情報はこれだけ。内戦に至る経緯や反乱軍の実態などは、登場人物の会話やニュースの断片から推測するしかない。そして車で出発してからは、リーたちにも何が待ち受けているか分からない。観客は4人と一緒に、戦場を通り抜けることになるのだ。
ワシントンDCまでの道筋には、焼け焦げた車が放置され、激しい局地戦にも遭遇する。いかにも不穏な空気が漂う場所もあれば、戦争などないかのように不気味に静まりかえった町もある。そこがどの勢力圏なのか、出会った人物たちの素性や所属など、全く分からない。画面はヒリヒリした緊張感に包まれて、片時も気が抜けない。
入念な音響効果が、戦場体験を迫真のものに高めている。銃撃音、爆発音、ヘリコプターのローター音などが大音響で響き渡り、平穏な風景が突然銃声に切り裂かれて度肝を抜かれる。そうした恐怖と共に、最前線に到達する高揚感も生々しく伝えている。銃撃や爆発に近づくにつれて興奮状態となり、最初は戦場の現実に泣きべそをかいていたジェシーは、前へ前へと突き進むようになる。
リーは目の前で起きる凶行に「自分は質問しない。他の人が質問するために記録する」と中立を標ぼうする。米国の分断や正義、ジャーナリズムや戦場の倫理といった問いについて、映画は一切の価値判断をしていない。観客にただ、戦場を体験させるのである。これ以上ないリアリティーで。アレックス・ガーランド監督。1時間49分。東京・TOHOシネマズ日比谷、大阪・TOHOシネマズ梅田ほか。(勝)
ここに注目
主人公たちが車を走らせる頭上には青空が広がり、美しい田舎の風景は牧歌的ですらある。しかしほんの少し視線を移すと、あちこちで煙が立ちのぼり、戦闘、拷問、処刑などの陰惨な現実が繰り広げられている。その強烈なコントラストと、誰と誰が戦っているのかもわからない戦争の不条理性が戦慄(せんりつ)を呼ぶ。また、観客の視点を担うキャラクターのジェシーは、野心満々だが経験の乏しい駆け出しカメラマンだ。そんなルーキーが血生臭い地獄巡りの果てに、皮肉な形で成長していくドラマも見応えたっぷり。(諭)
ここに注目
郊外のショッピングモール、緑豊かで風そよぐ自然、大都会などアメリカらしい光景の中で描かれる残忍なシーンのリアリティーは衝撃的だ。相手が誰かもわからず撃ち合う農場での恐怖。分断の一因でもある「どういうアメリカ人だ?」というセリフの現実性……。終盤の銃撃戦を含めジャーナリストの視点で見せることで、暴力の臨場感が駆け抜ける。連邦議会襲撃事件であらわになった無秩序と崩壊への不安が背景にある。さらに、過去に行ってきたアジアや中東での武力衝突のすさまじさも想像できる。(鈴)