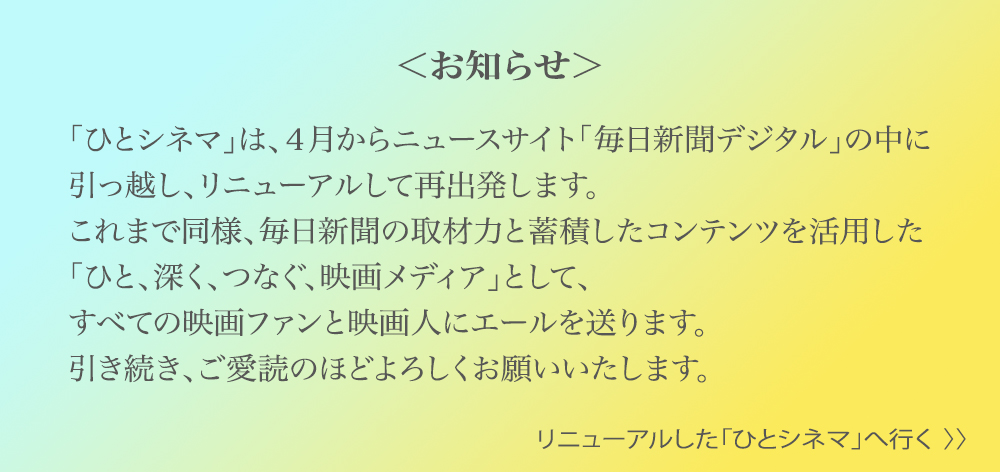毎週公開される新作映画、どれを見るべきか? 見ざるべきか? 毎日新聞に執筆する記者、ライターが一刀両断。褒めてばかりではありません。時には愛あるダメ出しも。複数の筆者が、それぞれの視点から鋭く評します。筆者は、勝田友巳(勝)、高橋諭治(諭)、細谷美香(細)、鈴木隆(鈴)、山口久美子(久)、倉田陶子(倉)、渡辺浩(渡)、木村光則(光)、屋代尚則(屋)、坂本高志(坂)。
「ヒューマン・ポジション」© Vesterhavet 2022
2024.9.13
この1本:「ヒューマン・ポジション」 繊細さに硬派なひと筆
日本で公開される北欧の映画、数は少ないし派手な大作もないけれど、見て良かったと得した気分になる作品が多い。フィンランドのアキ・カウリスマキ監督の一連の作品もそうだし、スウェーデンのロイ・アンダーソン監督のシュールなコメディーとか、ノルウェーなら現代を生きる女性を活写した「わたしは最悪。」、静かなホラー「イノセンツ」も忘れがたい。語り口が落ち着いているし、映り込む風景や町並みも端正だ。「ヒューマン・ポジション」は、北欧らしいミニマリズムにちょっぴり硬派なひと筆を加えている。
ノルウェーの港町オーレスンが舞台。夏の間、かつて働いていた新聞社に復帰した記者の女性、アスタ(アマリエ・イプセン・ジェンセン)が主人公だ。小さな地元紙らしく、アスタは何でも取材する。地元のホッケーチーム、景観保全を訴える市民団体、トンネルの事故。現場に行って話を聞く。ある時、閉鎖された工場に勤めていた難民申請者が強制送還されたという記事を読んで、気になりだした。続報を書こうと取材を始める。
といって、新聞記者の目を通して難民問題を告発する、いわゆる社会派映画とは趣が違う。アスタは熱心に取材に取り組む一方で、女友達のライヴ(マリア・アグマロ)とネコとの暮らしも大切にしている。カメラは固定されて動かず、激しい感情が噴出することもない。少し離れて、アスタの生活と仕事を見つめている。
映画の後半、アスタが行方不明の難民、アスランの足取りを追っていくうちに、豊かで福祉も手厚いノルウェー社会にも、陰があることが分かってくる。まなじりを決して、という大上段の構えではなく、生活者の目線から、心地よい日常のすぐ隣に不条理な陥穽(かんせい)があることを静かに示す。ともすれば理想化され美化されがちな北欧のイメージにとどまらず、現代の人間の置かれている場所を映し出す。繊細ながら、骨がある。
アンダース・エンブレム監督。1時間18分。東京・シアター・イメージフォーラム。大阪・テアトル梅田(10月25日から)など全国で順次公開。(勝)
ここに注目
アスタとライヴは、無理のない静かな時間を生み出している。2人の日常に、信頼関係と適度な距離感があるからだ。ラストショットの2人にも、心が和む。アスタは記者として復職し、少しずつ社会と向き合い、分け入っていく。世の中のゆがみがたやすく変わることはないけれど、アスタは動きを止めず、自身のスタンスを取り戻そうとする。そこには強固な意志が宿っている。無駄のない淡々とした描写からにじみ出る日常と生き方に、憧憬(しょうけい)さえ感じてしまった。(鈴)
ここに注目
「たいしたことが何も起こらない」映画は退屈になりかねず、長編として成立させるのは容易でない。しかし本作は固定カメラ主体のショット一つ一つが絶品で、港町を一望する高台の冒頭シーンから魅了される。アスタの通勤ルートであるジグザグの並木道、フェリーから捉えられた雄大な自然、物陰越しなどの謎めいたカメラアングルが印象深い室内シーン。さらに無人の風景が幾度となく点描され、うら寂しさが漂う。北欧ファンはもちろん、想像力をかき立てる繊細な映画を好む人にオススメの小品。(諭)